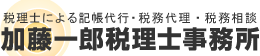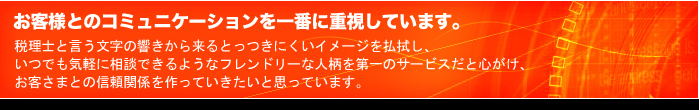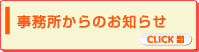所得の帰属
ある所得が発生した場合に、その所得が誰に帰属するかが所得税法上問題になることがあります。
例えば、父が歯科医として歯科医院を経営していたところ、息子が歯科医師となったため父の歯科医院で診療に従事し、収益と費用を父子で折半して確定申告をした場合にそれが認められるか、同医院で発生した収入は父に帰属するのか、それとも父と息子に帰属するのかといった形で問題になります。
所得の帰属に関して所得税法12条は「資産又は事業から生ずる収益の法律上帰属するとみられる者が単なる名義人であって、その収益を享受せず、その者以外の者がその収益を享受する場合には、その収益は、これを享受する者に帰属するものとして、この法律の規定を適用する。」と定めています。
要は、形式的な名義人に関わらず、実質的に収益を享受する者に所得税を課するということです(実質所得者課税の原則)。
上記の事例が争われた事件では、裁判所は実質的に所得帰属者を判断し、形式的には親子それぞれが別々に個人事業主として収益費用を折半して所得を享受していても、諸々の事情を総合考慮した上で歯科医院の経営主体である父に歯科医院から生ずる全ての所得が帰属すると判断しました(東京高裁平成3年6月6日判決)。
すなわち「親子が相互に協力して一個の事業を営んでいる場合における所得の帰属者が誰であるかは、その収入が何人の勤労によるものであるかではなく、何人の収入に帰したかで判断されるべき問題であって、ある事業による収入は、その経営主体であるものに帰したと解すべきであり(最高裁昭和37・3・16第二小法廷判決、裁判集民事59号393頁参照)、従来父親が独立で経営していた事業に新たにその子が加わった場合においては、特段の事情がない限り、父親が経営主体で子は単なる従業員としてその支配のもとに入ったものと解するのが相当である。」と判示しました。
本件の場合に特段の事情が認められるためには、親子の居住実態が完全に独立しているといえること、費用分担が明確に区分されていること等が必要でした。
本判決では上記の逆の事情が細かく事実認定されており、結果的に子を独立した所得帰属者とは認めずに、歯科医院の経営者である父にすべての所得を帰属させる結論に至りました。
親子関係に限らず、複数の者で共同事業を営む場合には所得の帰属に注意が必要です。
問題が生じる前に予めご相談ください。