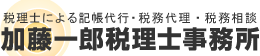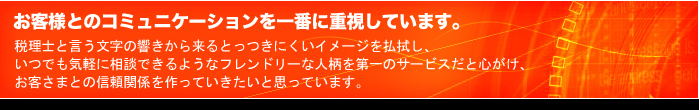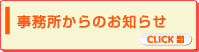海外親会社からのストックオプション
少々古い話題ですが、海外親会社からのストックオプションの所得分類については、平成17年1月25日の最高裁判決が有名です。
新聞等でも大きく報道されましたが、判決内容は原告(納税者)の完全敗訴でした。
ストックオプションとは
「自社の株式を一定の価額で購入することができる権利」のことで、会社が自社の役員や従業員に対して付与する権利です。
通常、株価が上昇した時に権利行使して証券市場で売却します。
売却価額と購入価額の差が、利益(課税所得)となります。
株価上昇と共に利益も莫大な金額になるので、権利保持者は会社業績向上に貢献するモチベーションが上がります。
例えば
権利行使株数100,000株、権利行使価額¥1,000、時価¥3,000の場合
¥300,000,000(売却価額)-¥100,000,000(購入価額)=¥200,000,000(利益2億円)
この利益が課税の対象になりますが、日本法人に勤務する納税者が海外の親会社から付与されたストックオプションの権利行使による利益が「給与所得」か「一時所得」になるか見解が分かれてきました。
どちらの所得として扱うかにより、納税額に大きな差が出ます。
サラリーマンお馴染みの「給与所得」では、給与所得控除があるだけです。
一方、偶発的な所得である「一時所得」は(利益-50万円)×1/2で計算します。
上記の例で利益が2億円の場合、給与所得と一時所得とでは税額にどれくらい差が生じるでしょうか。
納税額(基礎控除等は考慮外、税率は訴訟当時のもの)
給与所得で計算した場合
¥200,000,000-¥11,700,000(給与所得控除)=¥188,300,000
¥188,300,000×37%(税率)-¥2,490,000(控除額)=¥67,181,000(納税額)
一時所得で計算した場合
(¥200,000,000-¥500,000)×1/2=¥99,750,000
¥99,750,000×37%(税率)-¥2,490,000(控除額)=¥34,417,500(納税額)
納税額は約2倍もの差が出ます。
これについて課税庁(国税庁・国税局・税務署)は、平成10年まで「一時所得」であるとして納税者に指導してきました。
国税局職員が執筆した解説本にも明確に「一時所得」であると明記されています。
ところが平成11年頃より課税局は突如として「給与所得」である、と見解を変更しました。
そして修正申告に応じない納税者に対して追徴課税を行ったのです。
納税者の中には、一時所得税引後の利益で家を購入したりした人もいましたが、いきなり「過去の申告に間違いがあるから数千万円ないし数億円払え」と言われても釈然としないのは当然でしょう。
そこで国を相手取り行政訴訟が提起されたのです(100件以上)。
論点は
(1)雇用関係の無い海外親会社からのストックオプションによる利益が「給与」に該当するか否か
(2)過去に遡っての課税が妥当か否か(課税庁の指導経緯)
地裁では納税者勝訴の判決もありましたが、高裁ではいずれも敗訴。
そこで平成17年の最高裁による判決となりました。
結論から言うと、納税者敗訴。
判決内容は(1)について給与所得であるとした上で(2)については「重要ではない」として却下。
この最高裁判決には問題点があると考えます。
(1)の論点について、給与所得の定義として最高裁の判例(昭和56年)には、「雇用関係に無い海外の親会社」は含まれていません。
概念を拡大するならば再定義が必要なのにそれが今回の判決にはありません。
(2)の論点について、憲法84条では「租税法律主義」が定められていて、全ての課税は法律に基づいて行われなければなりませんが、方針変更を理由とする過去に遡っての課税は、憲法上許されるのでしょうか。
今回の訴訟では「信義則」違反での訴えでしたが、「重要ではない」と内容の審理に入りませんでした。
平成17年の最高裁判決は、建前はともあれ裁量行政の典型である税務行政を追認するような判決で、どうも腑に落ちません。